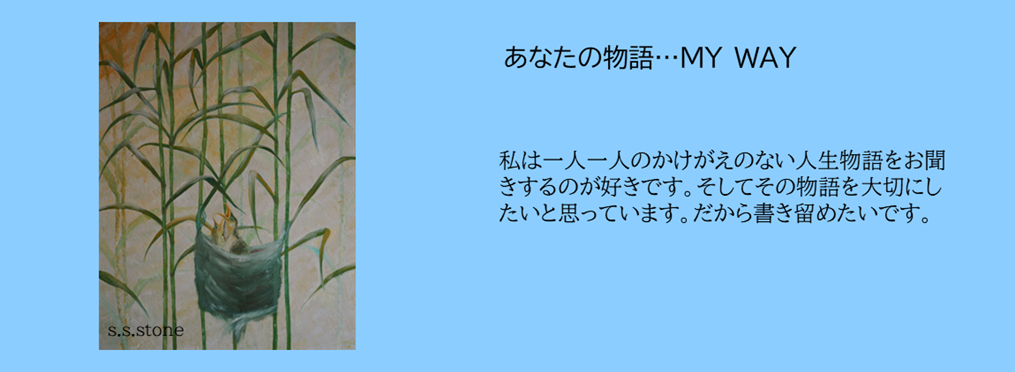
雑誌の編集をしているとき、「MY WAY」というコーナーを担当していました。「MY WAY」ではいろいろな方の人生物語を連載しました。最後の職場(高齢者施設)では、入居者さんの人生物語をたくさんお聞きしました。入居されるときに必ずお聞きするその方の「フェイスシート」はすでに人生物語です。毎月発行している「出会い通信」には「MY WAY」というコーナーで再度何人かの人生物語をお聞きし、連載していました。
私が37歳の頃、母が胃がんになり、入院した部屋の皆さんと仲良くさせていただきました。それぞれの人生物語をたくさん聞かせてもらいました。母が退院するときに、病室の皆さん5人がエレベーターの前まで送ってくださり、「何もかも、話尽くしました。聞いてもらってありがとう」と手を握ってくださいました。それからすぐ4人の方がご逝去されました。
私は出会った皆様の一人一人のかけがえのない人生物語を大切にしたいと思ってきました。まずは父の物語を掲載してみました。
<目次>
あなたの物語№1 ~いつも不足を言わず、家族に満足し「まあ、最高に幸せやね」が口癖だった~
あなたの物語№2 ~教員生活62年、「休まず、遅れず、働かずの弥一です」と弥一は胸を張る~
あなたの物語№3 ~それではと思い、好きな土地に行って働こうと思う…金沢から尼崎から東京~
あなたの物語№4 ~最後に思えたこと「生きてきたことこそが素晴らしいことなんだ。」~
あなたの物語№5 ~「大いに東京の生活を楽しんでいます。本当にありがとうございました。」~
あなたの物語№6 ~米作、ハルの物語(祖父母の物語)~
あなたの物語№7 ~母親の一つ一つの言葉を運命のような感じがした。歳がいけばいくほど母親のことを思う。母親は神・仏と同じ存在~
あなたの物語№8 ~『茨道 峠の明かり見えてきた』~
あなたの物語№9 ~「寿命が来るまで生きてほしいと言ってくれる人たちがいる」~
あなたの物語№10 ~「わしらみたいに年になると、わからんことも分かりたいという気持ちになるもんや」~
あなたの物語№11 ~これからの10年は自分のために好きなように生きたい~
あなたの物語№12 ~「たのんね」「じゃまない」の徳治だった~
あなたの物語№13 ~“ケセラセラ”明日は明日の風が吹く~
あなたの物語№14 ~私の終着駅が人生の楽園なので最高~
あなたの物語№15 ~「山の幸染め」は心を豊かにしてくれ、自分を支えてくれるかけがえのないもの~
あなたの物語№16 ~自然にまかせる、逆らわないをモットーに極上の孤独を満喫して生きる~
あなたの物語№17 ~「Danken Schon」という言葉をよく使い、「Danken Schon」で人生を閉じた~
あなたの物語№18 ~いつも何か楽しいことはないか考えている~
あなたの物語№19~だれも経験できないこともいっぱい経験してきたから、もう何にも不足はないよ。としは、「しあわせなや」「ありがとう」と幸せそうな顔をして、いつも回りの家族を幸せにしてくれた。~
あなたの物語 №19
~だれも経験できないこともいっぱい経験してきたから、もう何にも不足はないよ。としは、「しあわせなや」「ありがとう」と幸せそうな顔をして、いつも回りの家族を幸せにしてくれた。~

としは令和7(2025)年10月5日、22時45分、老衰のため、93歳の生涯を閉じた。ちょうど夫と同じ享年だった。
としは自分で縫った花柄の服を羽織り、家族とのいろいろな思い出の写真と大好きだった花に包まれて旅立った。としの法名は、「釋尼裁華」。
としは昭和7(1932)年4月16日、富山県黒部市沓掛に生まれた。5男6女の上から8番目。母親はとしが12歳の時、田んぼで倒れて亡くなった。としにとっての母親の思い出は、11人の子供と、親を亡くした姪2人の13人を育てながら、大きな百姓の家を切り盛りするために朝から晩まで働き続ける姿だった。また、戦地に長男を送った時の泣き崩れた母の姿、としの手を引いて何度も舞鶴港に出向き引揚げ船を待ち続け、帰ってこない我が子にすすり泣く母の姿。そして、空の骨壺の蓋を開けては毎日泣く母の姿だった。長男は海軍に所属し、昭和17(1942)年1月9日午後零時45分、中華民国海南島で戦死した。としが小学校の時、兵士に宛てた手紙を書き、戦地に手紙が送られた。偶然にも、その手紙を受け取った人が兄の骨壺を届けてくれた。骨壺が届いた2年後、母親が亡くなった。
としは女学校を卒業後、父親の希望で行儀見習いの為、14歳で東京足立区の実業家の家に半年間奉公に出された。奉公先では朝4時に起床し、10時就寝の生活だった。としには母親の不思議な記憶があった。朝方、その家の長い階段の途中で、としを見守ってくれている亡き母親の姿を、年を取ってもよく思い出した。
「その時のことを思い出すと、夢だったんだと思うがいけど、本当に母親が毎日見守ってくれたように思った。」
奉公を終え家に戻ったとしは、手に職を付けさせたいという父親の願いから、美容師か洋裁師を勧められた。としは小学校の頃から運針などが得意だったこともあり、洋裁の道を選んだ。ちょうど三女の姉夫婦が大阪で洋裁の仕事をしていたので、そこに修行に行くことになった。洋裁を習いに行ったにもかかわらず、子守や家事を主にさせられ苦労したが、2年半の奉公で洋裁の一通りの技術、製図から仮縫い完成までを身につけた。
17歳で実家に戻り、家で洋裁の仕事を請け負った。型紙を起こさず、布に直接チャコで製図して、洋服を縫えることが自慢であり、腕のいい洋裁師として地元で評判だった。
昭和26(1951)年、19歳の時、父親が決めた縁談で忠一と結婚することになった。忠一は亡き母の妹の養子であった。この時、としには好き合っている人がいたが、父親の言うことに従わざるを得なかった。忠一は幼少のころからとしの家に出入りし、家の仕事を手伝ったりしていたので、父親にかわいがられていた。忠一はとしのことを好いており、としが喜ぶと思って、盆踊りの時など村一番の美男子に自転車にとしを乗せるように頼んだという。
「結婚前は忠一も叔母さんの姑も、洋裁だけしてればいい、百姓などしなくていいと言われて結婚したがいけど、結婚した翌日から田んぼに出されたいちゃ。忠一は手もじゃで私の半分も仕事できんもん。しかたないちゃ。」
嫁いでから、毎日毎日辛い日は続いたが、25歳の時に長女が生まれようやく気持ちの整理がつき、子供のために島家で生きていこうと思うようになった。28歳で次女を出産した。
としは洋裁師として胃がんの手術をする62歳まで、農業をしながら洋裁店に勤めた。製図から仮縫い、完成までとすべて自分で出来る洋裁の達人。自分の服も姑の服も娘達の服も夜なべをして作った。娘たちは母親の作ってくれた服が自慢であった。娘のウェティングドレスや孫達の服も作った。62歳から胃がん、腸閉塞などで入退院を繰り返してきたが、70歳過ぎまでブティックやクリーニング屋の寸法直し等を請負い、80歳近くまで自分の服や子供たちの服を縫ったり、近所の人からお願いされて洋服の直しをしていた。
農業は米以外に、夫の希望で昭和33(1958)年から45年までたばこ栽培をした。昭和33年は長女の生まれた年で、娘のために稼ぎを増やしたいという夫の想いであったが、手もじゃの夫とのタバコ栽培は困難だった。長女も小さい頃から夏休みもなく手伝っていたが、としはその姿を見て心が痛かった。その後、55歳頃から62歳まで夫の思い付きで始めたネギ栽培も手伝った。米作りはなかなか忠一が辞めると言わなかったため、長女夫婦から収入より支出が大きいことを分かるように説明してもらい、忠一が81歳、とし76歳の時ついに辞めてくれた。
癌で入院した時も、「百姓をしなくていいし、子供家族がお見舞いに来てくれるし、最高に幸せやったちゃね。百姓をしなくてよくなってからの人生はバラ色やちゃね」と言っていた。
百姓をしながら、洋裁店に勤め、家事をこなし、夜なべをして服を縫う。としは料理も得意で田舎ではないようなハイカラなものも作った。カマンベール入りコロッケ、おはぎ、赤飯、いとこ煮、おから、魚料理、煮しめ、鶏のから揚げ、いもようかんなど、としの料理は天下一品だった。娘の遠足には孔雀のような巻きずしを作ったり、リンゴに娘へのメッセージをかいてサプライスしたり、粋なことも大好きだった。
姑を家で看取り(昭和42年、35歳の時)、舅も最後の最後まで寄り添って見送った(昭和56年、49歳の時)。朝から晩まで働き通しだったが、子供たちの成長が心の支えだった。田舎の周りの人が何と言おうと、娘たちがやりたいことは何でも応援した。命を懸けて娘たちを守ってくれた。
昭和63(1988)年、次女が結婚してから、夫婦2人の生活を送った。次女は夫が仕事で赴任していたブラジルに住むことになった。長女家族は埼玉県や茨城県水戸市に住んでいたことから夫婦でよく訪れた。孫娘が埼玉小児医療センターで心臓の手術をした時には、娘と一緒に病院の近くのウィークリーマンションにひと月滞在し、孫を毎日見舞った。平成5(1993)年、長女の夫は金沢に転勤になったのを機に、忠一・とし夫婦と養子縁組を行なった。長女家族が金沢に引っ越してからは行ったり来たりしながら過ごし、北海道、沖縄、奈良・京都、長野など長女家族との旅行を楽しんだ。
平成22(2010)年11月4日(78歳)のとき頚椎・頚髄症の診断、手術、リハビリのため金沢の5か所の病院を転々とし、7か月の入院後、としと忠一の強い希望で黒部の家に帰った。
黒部に戻ってからは、デイサービスを利用し、長女夫婦が2人の生活を支えた。
平成26(2014)年1月、とし82歳の時、孫娘の結婚式にハワイ旅行に皆で出かけた。夫婦2人共、初めてのパスポートを作ったり準備をしていたが、残念ながら忠一は直前に認知症状が悪化し、行くことができず、次女が旅行の間、忠一を看てくれた。としは孫娘夫婦と長女夫婦の5人で1週間のハワイ結婚式ツアー楽しんだ。結婚式、ディナーショー、潜水艦遊覧、クルージングなどと過密なスケジュールだったが元気だった。どの写真も元気で喜んでいるとしの姿がある。
同年2月、とし82歳の時、金沢市の長女家族の近くにあるサービス付き高齢者住に夫婦で入居し、忠一と隣同士の部屋でデイサービスを利用しながら暮らした。娘は毎日両親のもとを訪問し、2人の生活を支援した。しばらくは娘家族と外食したり、花見をしたり金沢での生活を楽しんだ。この生活は、1年5か月つづいた。忠一は歩行が困難になり、平成27年7月、入院治療をし、その後、地域密着型特養に入所となった。
としは平成30年2月、最初の施設が廃業となったため、近くの介護付きケアハウスに移った。翌年の平成31(2019)年3月31日の早朝転倒し、大腿骨転子下骨折を受傷し、手術とリハビリのため合わせて3か月間の入院をした。一旦はケアハウスに戻ったが、令和2年1月8日に夫の入所している地域密着型特養に移ることができ、それぞれ2階と3階に暮らし、家族の訪問時は一緒に時間を過ごした。2人は4年と8カ月ぶりに一緒の建物で暮らすことになった。としのことを大好きだった忠一にとっては幸な時間となった。
令和2(2020)年1月から令和5年5月の3年4ヶ月間、コロナウイルス蔓延のため面会ができなくなり、途中からリモート面会になった。コロナ禍の令和3年2月、熱発を機に忠一の身体状況が悪化し、亡くなるまで毎日、家族が短時間の面会が許され、としも1年ぶりに直に家族に会うことができた。その時、令和2年7月に生まれたひ孫(女の子)を抱っこすることもできた。3月12日、忠一は逝去したが、としが傍にいてくれたことは、奇跡のようなものだった。
その後も1週間に1度、娘夫婦はひ孫と一緒にリモート面会を続け、令和5年5月、3年ぶりに直に家族と面会できるようになった。令和5年9月に2人目のひ孫(男の子)が誕生してからは4人が毎週顔を見せてくれた。
「子供達にいろんなところに連れて行ってもらって、だれも経験できないこともいっぱい経験してきたから、もう何にも不足はないよ」とよく話してくれた。
としは自分の人生に満足し、家族を自慢に思い、不足を言うことはなかった。
いつも、「しあわせなや」「ありがとう」と幸せそうな顔をして、回りの家族を幸せにしてくれた。
令和7年10月5日
あなたの物語 №18
~いつも何か楽しいことはないか考えている~

「教室でいただくプリントを3回ほど読み返す。何回も読んでいるうちに頭に入ってくる。こないだの『脳生き生き教室』で勉強したドーパミンやセロトニンのこともよく分かるようになった。脳活性化プログラムに参加することが誇りで、参加することに満足している。これからも脳活性化を目指していきたい」といつも時子は言っていた。
若いときから時子は歌が好きだった。歌で救われていた。歌を歌ったら悩みなどは吹っ飛ぶ。よく歌っている曲は山中節。音楽のCDもたくさん持っており、周りに人にも聞いてもらっていた。カラオケ大会には衣装を自分で用意して挑んだ。歌に踊り、手品を披露し、イベントなど楽しいことにはすべて参加していた。
「相撲や政治等、世の中の情勢をテレビや新聞を通して把握している。またその内容を回りの方にお話できることが楽しみ。いつも何か楽しいことはないか考えている。いつも周りの人に何かして楽しませてあげたいと思っている」といつも楽しいことはないかと時子は考えていた。
時子は大正15年(1926年)10月に金沢市三谷村に生まれた。5人兄弟の上から3番目。尋常高等小学校、国立病院附属看護学校を卒業後、看護師として国立病院に55歳の定年まで勤務した。退職後も2カ所の病院に勤務し、70歳まで働いた。看護師人生50年、それが自慢の人生だった。
25歳の時、結婚し2男を儲けた。平成26年(2014年)12月、夫の逝去後長男と2人で暮すが、平成27年7月に介護付き有料老人ホームに入居した。平成30年8月からは介護を受けることになったが、令和2年(2020年)12月、88歳の最後の日まで「いつも何か楽しいことはないか考えている」という時子だった。
時子は若い頃、「母ちゃんのために家を建ててやりたい」と頑張った。それを実現できたことが自慢だった。
「父ちゃんが早死にしたもんで、お父ちゃんの代わりによく働いた。自分の生まれ育った家は村で一番の貧乏だった。」
父親が酒飲みで、家にはお金はなかった。母親が一人で働き、5人の子供を育ててくれた。父親は50歳代で田んぼの中で倒れ亡くなった。「たった一人で頑張っていた母ちゃんがかわいそうで、かわいそうで、大人になったらお金をためて母ちゃんに家も建ててやりたい」と国鉄に勤めていた兄と一生懸命頑張った。
山から木を切ってきて家の柱にしようと思ったが、その木が腐ってしまった。仕方ないので柱を材木屋から購入することになった。そのため予算がなくなり、壁塗りは壁屋に頼むことが出来なくなった。
時子は、壁屋の叔父に壁の作り方、塗り方を習った。土に藁と水を入れ混ぜる。その壁を踏んで、塗り上げる。村の人からは「20歳そこそこの女の子が男のような仕事をして、台風が来たら吹っ飛んでいくぞ」と言われたり、「借金して大工さん雇えばいい」と言われたが、病院の勤務を夜勤にしてもらい、家の外側と中側に壁を塗った。ついに間口3間、奥行き5間(1間は約1.8メートル)の家を完成させた。「村の人が家を見に来て、壁に体当たりしたがびくともしなかった。私は自信満々だった。母ちゃんは60歳で亡くなったが、自分たちが作った家に迎えることが出来て最高だった」と時子は喜んでいた。時子は兄が結婚するまでその家に住んでいた。
姉が国立病院の看護師をしていたが、「国家の病院だったので袴を履いて敬礼をして…その姿に憧れて看護師になろうと思った。また、とにかくお金を貯めよう」と時子は思った。
「看護師は自分にとって天職であり、息子も孫も看護の道に進んでくれたことは何よりもうれしい」と時子は言っていた。70歳になった時、息子たちから「そんな年取っているのに、もう働くのやめてくれ」と言われ、看護師を辞める決心をした。長男がスポーツ好きで相撲の県大会で1位になり、新聞に載ったが、そんな時でも仕事優先で応援に行ってやれなかった。そのことが今でも申し訳なかったと時子は思った。
「看護師の仕事は、元気になってありがとうと言って退院される人を送り出すことが喜びだった」と時子は言うが、現実は厳しい現場だった。時子が働いていた国立病院は石川県の結核療養所として昭和13年設立され、当初は結核治療に取り組んでいたが、昭和22年国立療養所への改編以降は神経難病や重症心身障害への専門医療を中心とした病院となった。
時子が国立病院に勤務したのは17歳頃、昭和18年。その当時は治療に有効な抗生物質(ペニシリン)はなく、亡くなる患者さんも多かった。戦後しばらくしてペニシリン系抗生物質は医療現場に提供されるようになったが、お金の問題で適切に薬を使えない人も多かった。
ある日、北海道出身の家族のいない患者さんが亡くなり、死後の処置をしたときに、幾重にもタオルがおなかに巻かれていて中に45万円が入っていた。「院長と相談をして北海道の兄弟の消息を探し、連絡をとった。兄弟は誰も、自分は年を取っているので引き取れないと言っていたが、お金の話をすると我も我もと言って引き取りに来た。なんとも複雑な思いだったが、自分の生まれた北海道の墓に入れるので良かったと」と時子は思った。
「この年まで生きて思うこと。本当の幸せは健康に勝るものはない。私の健康とは、施設の『エンジョイライフ~月の予定~』に書いてある活動に毎日参加できること。ここはいろいろなことを学べるところ。いくつになっても学ぶことが出来る。その幸せ」と時子はいつも思って晩年を生きた。
あなたの物語 №17
~「Danken Schon」という言葉をよく使い、「Danken Schon」で人生を閉じた~

宏は、腎臓、肺に小さながんがあったが、肺炎のため平成26年11月(2014年)に入院する直前まで妹の隣の居室で安心して最後まで自分らしい生活を送った。入院期間は18日間。88年の人生であった。
宏は、会話の中で「Danken Schon」という言葉をよく使い、「Danken Schon」と言って会話を閉じた。「Danken Schon」は宏のシンボリックな言葉であった。宏がこの言葉をなぜ好なのかというと、「この言葉を口にすると、顔まで明るくなるから」と話していた。
「今、生きていることに幸せを感じている。歩くことは健康の第一歩」とよく言い、足るを知り、感謝の毎日を過ごし、散歩を楽しんでいた。
平成19年4月(2007年)に妹のいる高齢者施設に入居した。「心の支えは自分自身。妹はお母さんのように頼りにしている」と言っていた。「なるようにしかならん」、「何も考えずに生きていく」という人となりと妹の存在、そして入居した施設を大変気に入ったこともあり、入居時にアルツハイマー型認知症と診断されていたが、あまり認知症状の進行は周りに感じさせなかった。最後まで自由に飄々とし、周りに振り回されることなく自分流に生き抜いた。定例会という2ヶ月に1度ほど、銀行員だったときの同僚とホテルランチを楽しんだ。友人夫婦も時々訪ねてきた。
入院の2日前、宏は自分の死生観をこう語った。
「一度、戦争で死ぬはずの体だったから死ぬのは怖くないが、この世からいなくなるのが不安。ここに住んでいる人は死ぬことをどう考えているのかとよく考える。生きる、死ぬは自分が決めることではなく、神様が決めるものと思って生きてきた。そして一日を幸せに送る努力をしなければいけないと思って生きてきた。」
宏は、昭和2年12月年(1927年)、金沢市に生まれた。60歳で逝去した父親は菓子職人、99歳で逝去した母親は銀行員だった。1男2女の長男。尋常小学校(6年)、旧金沢商業(5年)在学中、17歳で志願兵として海軍予科練に配属になった。舞鶴から鳥取そして倉敷、特殊潜航艇に乗り込む訓練を受けた。予科練は、旧日本海軍の「海軍飛行予科練習生」の略称で、航空機の搭乗員を養成するための制度で、14歳から17歳程度の少年たちを試験で選抜し、パイロットになるための基礎教育を行った。宏は予科練であったことを誇りに感じていた。
19歳で終戦を迎え、その後、貿易商を営む叔母の夫の仕事を手伝うため上京し、横浜のニューグランドホテルの中で九谷焼等の店を開いた。4年後、23歳の時、帰郷し、銀行に勤務した。その年、縁筋の1歳年上の妻と結婚し、2男をもうけた。銀行を退職し、55歳から70歳までベビー用品や人形などの販売店で総務・経理全般を行った。H12年、72歳の時妻逝去し、H19年4月まで独身の長男と2人で暮らした。趣味も多く、写真、スキー、スケート、ゴルフ、ダンス、読書。
火葬場へ向かわれる途中、施設の前で「Danken Schon」のプラカードで野辺送りを行なわれた。
あなたの物語 №16
~自然にまかせる、逆らわないをモットーに極上の孤独を満喫して生きる~

智津子は、1925年(大正14年)、輪島市にて生まれた。3女3男の一番上。金沢の師範学校を卒業し地元の小学校に勤務した。1948年(昭和23年)に漆器販売業を自営する夫と結婚し、1男2女をもうけた。教師を32年間務め54歳で退職。1982年(昭和57年)、57歳の時、長男の住む大阪府寝屋川市に住まいを移した。関西には親戚も多く、大阪で会社を経営していた妹の手伝いもしたりした。1992年(平成4年)、67歳の時、がんで長く患っていた夫が逝去。翌年、長男と兵庫県に家を建て、長男家族と同居した。2007年(平成19年)、長男が脳出血で亡くなり、その後家を出る決心をし、長女のいる石川県で住まいを捜し、9月に金沢の高齢者施設に入居した。
智津子は小学校の頃、加賀友禅の絵描きになりたいと思った。
女学校の頃には、数学と理科に興味を持つようになり、東京の大森にある理学専門学校に進学を希望した。経済的に無理かもしれないと思ったが、試験だけは受けたいと思い受験することにした。受験番号も届き、試験の準備をしていたが戦況が厳しくなり、試験延期の知らせがきた。奇しくもその受験日に東京大空襲が起きた。
女学校の担任から、「教師になって『第二の国民』を育てる道」を勧められたことがきっかけとなり、教師になる道を選んだ。智津子は「子供は、大人の気づかない当たり前すぎたところに面白みを見つける。道徳の授業などでは思いもよらない展開になったりと、子供の感性に驚かされた。子供たちと過ごした時間は、毎日がワクワクし、面白かった」と当時を懐かしんだ。
「息子の命日がくると思い出して暗くなる。年々、悲しさも弱くなってきているが忘れることは出来ない。でも暗い性格だとは思っていない。お笑いも好き。洋服もなるべく明るい色を選んで着ている。見た目は平凡そうに見えるが、心の中はパーッとはじけるようなタイプ」と智津子は自分のことを表現した
「心の支えは、なんといっても子供たち。子供も孫もひ孫も優しい。自分が残っても、先逝っても辛いと思い、子供に逝く時は一緒と言ったら、それは無理と言われた」と冗談を言いながら娘と笑い合った。
入居して1か月、体調が悪く狭心症の疑いから、救急外来に受診した。智津子は医師に「私はいつ死んでもいいという覚悟ができているので、ややっこしい治療はいらない」とはっきりと訴えた。
智津子は「人間としての原理。生まれたら死ぬ。早いか遅いか時間の問題。自然にまかせる、逆らわないをモットーに生きている」と語った。
智津子の「友禅の絵描き」になる夢は叶えられなかったが、教師を辞めてから再び絵を描き始めた、部屋から見たえる風景や身近にある静物を描き続けていた。
「孤独が趣味」という智津子のお部屋にはいろいろな本が並んでいた。
「本が心の支え。本とともに生きていく」と言っていた。政治、経済のことが好きで本や雑誌を読む。本が傍にあることが至福。本から学び、共感し、豊かに時間を過ごす。『北陸の資本主義』(清丸惠三郎)、『極上の孤独』(下重暁子)、『冥界からの電話』・『九十歳。何がめでたい』(佐藤愛子)、『お地蔵さまのことば』(吉田さくら)、『シルバー川柳』などの書物が、本棚や、テーブルに所狭しと置かれていた。
「ここにいるからこそ一人で好きなことをして『極上の孤独』を満喫している。一人で自分の人生を自分らしく過ごしているが、毎日、時間が足りないと感じている」と、2021年6月に亡くなるまで『極上の孤独』を満喫していた。
あなたの物語 №15
~「山の幸染め」は心を豊かにしてくれ、自分を支えてくれるかけがえのないもの~

剛は1930(昭和5)年1月、小松市に生まれた。2男1女の上から2番目。尋常高等小学校、国民学校卒業後、石川県県立工業(応用化学科)に入学したが、学徒動員で工場で働いた。戦後、18歳から48歳に30年間、精練会社に勤務。リストラされて退職した。その後、自営をしたり、鉄鋼所、旅館に勤務した。28歳の時、結婚し、1男1女をもうけた。
剛は、若いときに友人や親戚から裏切られ、大変辛い時期を過ごした。妻の弟が、剛の留守の時に「家の権利書を持ち出し、800万円盗られてしまった」。またバブルの崩壊でリストラにあった。それも剛は組合員の副会長をしていたが、たまたまその時期に昇進し、組合員でなくなっていたこともありリストラの対象になった。その時に友達2人と事業を起こしたが、その友人はお金を持って逃げてしまい、剛が負債を抱えた。その時にお金をどうすることもできなく、金沢の友人2人から300万円借り、借金を返済した。そのお金を今も返済できず、その友人に不義理をしていた。退職金の1千万円も家もなくなり、娘は中学校を卒業し就職した。自力で東京に行って夜間高校を卒業した。「子供達になにもしてやれなかったという」思いなど、自分の人生を悔やむことが多かった。もともとは「プラス思考の人間だけど、これらの過去は取り返しがつかない」と剛は言った。現在、迷惑を掛けた友人にどのように謝罪をすればよいか苦悩していたが、晩年天理教の従兄弟に相談し、友達と再会し深くお詫びすることができた。
子供が成人後は妻とで金沢で妻と2人で暮らしたが、平成6年、64歳の時、長男と長女が住む東京に上京し、4人で暮らし始めた。地域の絵手紙、健康体操、山の幸染めサークル活動等、積極的に参加する面もあった。特に山の幸染めは生きがいを持って打ち込んでいた。平成10年、妻が逝去後、
剛が金沢に戻ることになったいきさつは、息子と娘がサラ金に引っかかった時期があり、三人三様にこれから頑張ってみようと誓い合って、別々の生活をすることになった。
剛は、平成17年9月、75歳の時、金沢の介護付き有料老人ホームに入居することになった。息子はイラストレーター・漫画家志望で収入も安定していないが、もう10年東京で頑張ってみたいと言っていたので、一人で金沢に帰ることにした。年金で生活は出来るが、困ったことがあれば、妹が経済的な支援をしてくれると剛は妹を頼っていた。
施設入居後は、平成19年、長女が結婚し女の子の孫が生まれた。孫との電話を生きがいに思っていた。長男は、洗濯の配達のバイトをしながら漫画を描いていた。
平成27(2015)年9月、85歳の時から介護のサービスを受けたが、できる限り自立した生活を送っていた。そっくりな兄の訪問を楽しみにし、妹の支えが心にしみた。施設の教室活動や催し物、懇談会にはほとんど参加し、部屋では平成21年8月から「山の幸染め」を通信教育で一から学びなおし、精力的に取り組んだ。花壇の作業も「山の幸染め」のために行ってきた。手始めはハンカチの作成し、毎年新作を施設の文化祭で展示した。剛にとって「山の幸染め」は心を豊かにしてくれ、自分を支えてくれるかけがえのないものだった。
平成29年2月に亡くなった。最後まで妹夫婦が責任もって寄り添った。葬儀の時は長男が妹の支援で喪主を果たすことができた。
あなたの物語 №14
~私の終着駅が人生の楽園なので最高~

周りから優男と言われていた尚義は、83歳から92歳で亡くなるまでの9年間、高齢者施設に入居していた。その場所を「人生の楽園」と呼んでいた。
施設で行われていた「健康体操教室」、「本を楽しむ会」、「合唱の会」、「囲碁将棋ゲームサークル」、「レコード鑑賞会」、「認知行動療法プログラム心を見つめるレッスン」、「脳いきいき教室」、「カラオケを楽しむ会」、催しもの、懇談会など、施設の毎日行われる教室活動に参加していた。
朝5時に目覚め、5時30分頃ふとんから起き、教室活動を中心にした毎日で、月から金まで開かれていた喫茶には欠かさず出かけ、入居者仲間との語り合いの場になっていた。
尚義は、何もない時は殆どテレビを観ていた。ニュースが主で、スポーツニュースも欠かせなかった。何事においても几帳面で、たばこも朝8時、昼12時30分、16時30分、19時30分の4回で各時間1本と決めていた。晩酌はしないが、小腹がすくので、買ってきたうどんやもみじこ(たらこ)を電熱器を使用し作って夜食にしていた。
通販で取り寄せた1950から1960年代の洋画DVD(40本)を観ると心が躍った。「1本1本を時間のある時に一気に観たいので、なかなか観る事が出来ないが、映画を見るとわくわくする」言い、映画談議をよく始めた。ハンフリー・ボガード、ジェームズ・スチュアート、イングリッド・バーグマン、ジョン・ウエイと俳優名も次々に出てきた。「ローマの休日」 「風と共に去りぬ」 「カサブランカ」 「シャレード」 「哀愁」 「第三の男」 「市民ケーン 」 「ニューオリンズ」 「素晴らしき哉、人生!」「ナイアガラ」 「キング・ソロモン 」「ウィンチェスター銃’73」「折れた矢」と映画名も次々出てきた。
介護を受ける2年前までは、外での移動手段は主に自転車を使用していた。「昔から比べてペダルが重くなったが、自転車があれば風に吹かれて自由を味える」と言っていた。
尚義は富山県の城端町で大正9年12月(1920年)に生まれた。姉が2人いて末っ子だった。尋常高等小学校卒業後、金沢にあった父親の米屋で働いた。15歳の頃、米屋のある金沢市に家族で移り住んだ。尚義が18歳頃、父親が52歳で逝去し、母親と米屋を続けた。20歳の時結婚し、2男2女をもうけた。長男は幼少頃に逝去した。23歳、兵役で入隊し、中国、ベトナムの戦地に赴いた。終戦後1年間捕虜生活を送り、昭和21年(1946年)帰国した。
金沢に戻り、食糧営団(後、食料公団)で8年働き、独立し販売店を営んだ。40代になり、「自営業を辞めたい、勤め人になりたい」と思い始めた。昭和42年48歳の時、広島の戦友に家業を手伝って欲しいと言われ、単身広島へ移住した。友人の商売は小さなお菓子屋だったので、尚義は想像していたものと違っていたので失望した。それでも、広島で気の合う人に出会い、金沢には帰らず、製缶工場に昭和61年(1986年)、65歳まで働いた。「広島で、3人に恋した」と言う尚義は、その後も10年金沢には帰らず、広島に30年近くも暮らした。
75歳の時、金沢に戻り、アパートを借り妻の家と行ったり来たりしながらひとり暮らしをすることにした。平成15年11月(2003年)から、長男の誘いで同居したが、長男となかなか意見が合わなかった。平成16年7月、83歳の時便利のいい高齢者施設に入居することに決めた。平成21年8月妻が逝去した。過去を多く語らなかったが、尚義は「終着駅が人生の楽園で最高」の時間を過ごした。
あなたの物語 №13
~“ケセラセラ”明日は明日の風が吹く~

悦子は85歳まで独居生活を続けるが、食事が心配と思う姪の勧めで2013年(平成25)4月に高齢者施設へ入居した。
「兎に角、ここが楽しい。いつも“ケセラセラ”明日は明日の風が吹くと言う気持ち。妹家族やここの職員がいいのにしてくれるから、何にも心配はいらない」、「三度三度のごはん、何もしなくて食事が食べられること、なんでも美味しくいただけること、眺めのいい間取り、好きなお風呂に毎日入れること、ここにいることが幸せ。ここが私の城、終の棲家です」と悦子はよく言っていた。
悦子は昭和11年5月、金沢市金石に生まれた。1男3女の4人兄弟の上から2番目。日本通運に働いていた父親が40代でなくなり、その後、母親一人で一生懸命働いて子供を育てた。悦子は母親のことを「一所懸命働く人で、大変優しい人だった」と思っていた。
中学卒業後、金石郵便局で電話交換手をしながら夜学の中央高校に4年間学ぶ、卒業後も金石郵便局に勤務し、その後、金沢の日本電信電話公社(現、NTT)の市外電の電話交換手として定年の55歳まで勤務する。
悦子の時代は、電電公社では電話交換取扱者という資格がないと(外線の)交換手はしてはいけなかった(1984年に廃止)。手動の電話交換台が使用され一組の電話プラグを適切なジャックに差し込むことにより、電話回線を接続する業務を行っていた。きつい仕事と言われていたが、悦子は電話交換手の仕事が好きだった。職場の雰囲気も同僚もよかった。
悦子は小学校の頃から背が高くて、一番後ろで目立っていた。性格は「お節介焼きで、人を構いたいほう」でもあるが、「人は人、周りの人を信用して任せることが出来ことが得意なところ。なるようになる、ケセラセラ」という人物でもあった。
「若い時は、体重が70キロあり、結婚は考えなかった」とケセラセラ(だからあれこれと気を揉んでも仕方がない)ということで独身生活を送った。
「友達と海外旅行に出かけていたころは楽しかった」と言う悦子は、仕事を辞めてから毎年春、秋に海外旅行を楽しんだ。旅行先で友達になった人と、毎回約束して一緒に海外旅行のツアーでいろいろな国に行った。一つのツアーが終わると、旅行会社から案内が届く、そこから2人で相談して次のツアーに申し込むという感じで海外旅行を楽しんだ。「どこに行ったか国の名前は思い出せないけど、テレビで外国の風景を見るとあそこにも行った、そこにも行ったと懐かしく感じる。自分で計画したり、調べたりしていかないので、景色を楽しむという旅行だった。イタリア、フランス、ペルー、チリなど世界を巡った。特にペルー、チリへは何度も旅行した。定年から70歳頃まで年に2回海外旅行を楽しんだということで、30回以上の海外旅行をしたことになる。海外旅行の前後は東京にいる妹の家に2か月ほど滞在するのが習慣になっていた。
施設の秋の小旅行で加賀のかぼちゃ村のイタリアンレストランで食事をした時、壁に掛かった絵や写真を見て「行ったことある」と思わず声を上げた。また、「ロートレックの絵ですね」と悦子は指をさす。箸も添えてもらったが、フォークとナイフでメインの肉料理も、付け合わせもすべて優雅に食事をした。周りの人はそのフォークとナイフさばきのすごさにびっくりした。
悦子は毎朝6時半にラジオ体操をして、談話コーナーのカーテンを開け廊下を散歩する。外での散歩はできないが、廊下が散歩道。ケセラセラ(成り行きに任せてしまうのがよい)が悦子の持論。
「強みはくよくよしないところ❕」
「年金が入るので、お金の心配がいらないこと❕」
「妹・姪っ子家族にまかせっきり❕」
「教室で一緒になった人と楽しく会話できる❕」
「お風呂で一緒の方とも楽しくやっている❕」
「戦争とかあり、苦労して今がある。だから今、幸せに生きていられる。悔いもない。感謝している。いい人ばかりなので満足している❕」
「ここにいたら心配事も悩み事もない。過ぎ去ったことはくよくよしない性格。これ以上何を望めばよいかと思うが何もない❕」
「命のある限り、ありのままに生きていきたい❕」
と悦子のケセラセラ節がつづく。

あなたの物語 №12
~「たのんね」「じゃまない」の徳治だった~

徳治は、平成16(2004)年6月に有料老人ホームSに入居し、平成21(2009)年5月、85歳で逝去するまでの5年間を過ごした。普段は言葉が少なく、「たのんね」「じゃまない」をいろんな場面で使っていた。悩み事や心配ごとはないか尋ねると「なんもない。心配ぐらいあってもよさそうだが、ところがない」といつも応えた。
朝起きて洗濯、掃除に始まり一日のスケジュールを黙々とこなした。衣類のたたみ方にも流儀があり、アイロンを掛けたようにきちんきちんたたんだ。そんな物静かな徳治だが、歌をうたう時は軽妙洒脱だった。「きっと、若い頃はよく遊んだ方だろう」と噂されていた。歌の始まりは、はにかんだような感じでなかなかうたが出てこないが、一旦スイッチが入ると大きな声で次から次へと歌が飛び出す。十八番は「芸者ワルツ」だった。

施設のツアーには毎回参加していたが、職員がお誘いすると、はにかんだような顔で「よわった」と返答するが、職員が何度か声をかけると、「よわるんやちゃ」といいながら参加費のお金をぽんとテーブルに置いた。毎回そのやり取りで、年に2回のツアーを楽しんだ。ツアー中は「最高や」と繰り返し言った。
徳治は大正12(1923)年11月、石川県押水町に生まれた。8人兄弟の長男。尋常高等小学校卒業後、東京の電気工場に勤務したが、戦争のため航空隊の移動修理版として、浜松、福井など転々とする。昭和25(1950)年地元の北陸電気工事に勤務し、57歳で退職した。58歳の時、脳梗塞で倒れたが、その後76歳まで農業を続けた。昭和25年に幼なじみの妻と結婚し、1男2女をもうけた。妻と一緒に桃やいちごを作り、子供や近所の方に配って楽しんだ。平成15(2003)年9月、妻逝去により独居生活となり、息子に施設への入居を勧められ本人も了解した。
息子が叔父から聞いたという徳治の逸話がある。「徳治が十代で東京に行ったのは歌手になるためだった」。息子にとっては信じられないことだったが、古い家には蓄音機やアコーディオンオルガンなど音楽に関するものがいくつもあった。
息子は「父親とは若いときに別れて、関わりはあまりませんでした。母親が亡くなり、脳梗塞の障害がある父親をどうしようか考え施設に入居をすることにしましたが、ここに来てからようやく父親と話をするようになりました。本当のところ、父親がどんな人間なのか分からないままにきました」と言う。
徳治は何かにつけ「お父さんに聞いてみて」と言い、息子を頼りにしていた。
あなたの物語 №11
~これからの10年は自分のために好きなように生きたい~

ツヤは大正5年(1916年)1月、金沢市に生まれる。1男3女の4人兄弟の3番目。尋常小学校を卒業後、紙漉き、奉公、機織り等の仕事をした。20歳の時、4歳上の夫と恋愛結婚し、2男をもうける。結婚後、二人で自転車屋をした。戦中、夫は何度か戦地に出兵し、昭和19年(1944年)、ニューギニアで戦死した。ツヤが28歳の時だった。夫が亡くなってから、しばらく自転車屋を一人で続けたが、その後鉄工所、近江町の店に勤務し、女手一つで子供を育て上げた。食糧難や経済混乱のなかで子供を抱えての生活は大変に厳しいものだった。何度も心が折れそうになったが、子供達の寝顔を見、将来に思いを馳せ、これではいけない駄目だと、負けてはおしまいだと気を取り直し、歯を食いしばり懸命に働き続け、生き延びることが出来た。
ツヤは長男夫婦と同居し、仕事を辞めてからは孫の世話をし、家事を行い家族の生活を支えた。ツヤは87歳の時、「孫が一人前になるまではと思って家で頑張ってきたので、これからの10年は自分のために好きなように生きたい」と思い、自分で介護付き有料老人ホームを探し、平成15年(2003年)2月に入居した。長男夫婦は母親の行動に驚いたが、本人の希望を叶えたいとのことで、離れて母親を見守った。
ツヤは石川護国神社の諸祭典に参列し、夫の御霊に手を合わせつづけた。特に「春秋大祭」、お盆に行われる「みたま祭り」には何があっても出かけた。護国神社は家族のために尊い命を捧げ戦死された方々の御霊を特に尊んでご英霊と称え、御祭神としてお祀りし諸祭典を執行している。
ツヤは心臓に大きな動脈瘤があり、突然死が訪れるかもしれないということを知りながらも、死を恐れず、自分のスタイルを変えず、平成19年(2007年)1月に亡くなるまでの4年間、ホームで自分らしく最後まで生き抜いた。
心筋梗塞・心不全で病院に搬送され、その時点で難しい状況だったが、奇跡的に持ち直し、「一日も病院にいたくない。ホームに帰る」と繰り返し言い、担当医を困らせた。亡くなる1週間前の様子はホームに戻られるぐらいの勢いがあり、奇跡が起こりそうな感じだった。「リハビリもうまくいっているし、ここまで来たら、先生のいうことをしっかり聞いて、ホームにもうすぐ帰るから、たのんね」との言葉が最後になった。2カ月の入院だった。
長男は荷物の片づけの時、「このホームは入居者の福祉を考える所でもあり、家族の福祉も実現してくれた所」と語った。戦後、28歳から女手一つで家の家計を立て、2人の息子を育てたツヤ。だれにも弱みを見せない逞しく、強い人であり、本心を言わない人だった。
「母親が家を出て家族がお互いに距離を置くことで、兄弟が自分の目でお互いを見ることが出来て50年ぶりに再び“兄”と“弟”になれた。酒を酌み交わすことができるなんて夢にも思っていなかった」、「母親のことで妻に負い目があり、いつも一歩下がったところで申し訳ないと思っていたが、母親と離れて初めて肩を並べることができた。本当の夫婦になれた」(長男)
ツヤの家族の場合は、このホームは家族の再生の“場”でもあった。
あなたの物語 №10
~「わしらみたいに年になると、わからんことも分かりたいという気持ちになるもんや」~

外次郎は、96歳の時、息子の住む金沢の施設へ移り住んだ。家族は外次郎のことを「今も自分のことはすべて自分でできる人物。自立し、人生を過ごし続ける人。自分で納得しながら進むタイプ」と言った。
外次郎は2004年(平成16)年5月から2011年(平成23)1月、104歳で亡くなる6年半の間高齢者施設で暮らし、施設の応援団長的存在だった。
外次郎は高齢者である当事者として「年を取るということ」についていくつもの「外次郎語録」を残した。特に感銘を受けた言葉は、「わしらみたいに年になると、わからんことも分かりたいという気持ちになるもんや」である。
99歳の時、「99歳、夢のようです。はやから100歳になろうなんて考えていなかった。これからは周りの皆さんにできるだけ迷惑を掛けないようにやっていきたい。5~6年前から徐々に体が衰えてきてはいましたが、去年まではあまり気がつきませんでした。皆さんも、私ぐらいまで生きれば、一緒のことを感じられると思います。お金には不自由ないですが、肉体的にさみしい。どなたもいっしょでしょうけど、これからは一日一日を考えて生きます。『今日も一日済んだ』『今日も一日始まる』という感じで過ごしていこうかねぇーと思っています。」
外次郎は毎日、夕刊が届く頃にフロントに来て、気の合う入居者と時事懇談を活発にしていた。現在何が世の中に起きているのか、どんなことがブームなのか、きれいな“おねいさん”が出ていないか、隅々まで目を通し、分からないことは回りに聞く、それでも腑に落ちないようだったら、パソコンを指さしこれで調べてほしいと依頼する。毎日 “外次郎節”が炸裂していた。ちなみに外次郎は「わしは顔が細いから丸い顔の女の人が好きやね」ということだ。
外次郎は、1908年(明治41)1月、石川県小松に生まれた。尋常高等小学校卒業後15歳から東京の陶器問屋で丁稚奉公をしたが、17歳の時、関東大震災のため小松に戻り、瓦の工場に勤務する。19歳の時、国鉄の入社試験を受け、念願の国鉄職員となり、55歳の定年まで車掌、助役として勤務する。その間、東京、大阪、新潟等と転勤生活を送り、40歳の頃、金沢に暮らすも、戦争の状況が厳しくなり、羽咋に居を移した。その後、日本交通観光社で75歳まで勤務し、主に修学旅行の添乗員をした。
車掌をしていた頃の楽しみはコッペパンだった。戦時中車内販売でコッペパンを販売しており、販売は一人1個と決められていたが、余ると4~5個分けてもらっていた。大阪での仕事中B29の爆撃に遭い、自分は防空壕にいち早く逃げたが同僚が逃げ遅れ亡くなった。「何でもあるもんや。」
25歳の時、知人の紹介で羽咋出身の妻と結婚し、一女一男をもうける。
妻は、和裁の先生をしていた。また花の会の役員もしていたがその関係で、菊を作っていた。外次郎はその手伝いをして川から砂を取ってきて粘土と混ぜ土を作ったり、鉢を動かしたり・・20年程続けていた。仕事が一昼夜交代で時間があったからできた。
「年老いて 頭ぼけたが 気は元気」外次郎の最後の句。
あなたの物語 №9
~「寿命が来るまで生きてほしいと言ってくれる人たちがいる」~

はつは、大正2年(1913年)10月25日、福岡県糸島群北崎村に生まれる。1男5女の6人兄弟の末っ子。尋常高等小学校卒業後、農業の手伝いをする。実家は庄屋で、人を雇って農業をしていた。本人は、看護婦になりたくて福岡市の病院で見習いをするも、長続きせず20歳頃、英語を話せるようになりたいと思い、神戸の外国人経営の食品店に勤務する。YMCAでも英会話を習う。戦争が激化し、福岡に疎開する。戦後、福岡市で進駐軍のオフィスで電話交換手の仕事をする。しばらくして再び神戸に移り住み、神戸の進駐軍のオフィスで電話交換手をする。23歳の時、中国系の会社に勤務している金沢出身の松男と結婚する。子供には恵まれなかった。結婚後、金沢に移り、夫の母親と同居する。夫は片町の洋服店に勤めた。はつは進駐軍の電話交換手の仕事をしばらく続け、その後専業主婦となる。夫が平成16年(2004年)6月2日(93歳)に亡くなり、その後独居生活となる。平成17年(2005年)3月5日、家の老朽化と本人が年齢的に「こういう所に入る年かな」と思い有料老人ホームの自立型の居室に入居した。保証人は甥の嫁。
はつは、「何事も天に任せている。考え方でどうにでもなる。だけど、人間というのは難しい。いろいろな人が居るが、自分はいろいろな経験をしてきたから今がある。身内が居ないので、自分がしっかりしないとどうしようもない」と思い生きてきた。谷口雅春の思想、『生長の家』を信仰している。
はつは、特定の人とのお付き合いはしない。自分は自分。金沢の人は、気持ちを心に持ったまま過ごしているようだ。自分は直ぐに何でも言っているので、周りからは嫌われているかもしれないと思っていた。
平成19年(2007年)7月、末期の胃癌で、貧血のため転倒、腰痛と熱が続きそのまま9月20日入院となる。入院中病棟の主治医から本人同席のインフォームドコンセントが3回行われた。延命治療はしないという本人の意志に従い、今後の予測されるリスクについて一つ一つ医師との確認作業が行われた。結果、「痛み・苦痛の緩和に必要な治療は行う」「人工呼吸はしない」「心臓マッサージはしない」など細かい確認が本人に行われた。7カ月の入院の間、痛み・苦痛の緩和に必要な治療ということで輸血と胃ガンによる吐血の苦痛を取り除くためにステント治療が行われた。不運なことに身体的に安定していた時期に転倒し、大腿骨転子骨折、手術を受けることになった。
はつは、入院してから有料老人ホームの職員(ライフサポーター)と深い関わりが始まった。はつは、生きなければならない意味を職員と一緒に考えた。入院当初や骨折後、また吐血後は「死にたい」「なぜ、早くお父さん迎えに来てくれないのか」「わたしの業や」と繰り返し言っていたが、「自分は一人じゃないこと。人生の最後に出会った人たちがいること」「寿命が来るまで生きてほしいと言ってくれる人たちがいること」などちょくちょく見舞いに来てくれる施設の職員との会話を通して実感していく。それはとってつけた「生きる希望」かも知れないが、はつは苦しみながらも、以前より自分のことを話すようになった。
最後の日の断末魔の中、「私を待ってくれている施設に早く帰りたい」と何とも言えないうれしそうな顔をして職員に伝えた。
平成20年(2008)4月26日未明、はつは他界した。享年94歳。はつの死に顔は、先日の苦しい様子から想像できない穏やかな顔をしていた。「お父さんに迎えられてうれしそう」に旅立ったはつは、希望通りに大学附属病院に献体となった。
あなたの物語 №8
~『茨道 峠の明かり見えてきた』~

義紀は1931年(昭和6年)4月、富山県小矢部市で生まれる。兵隊になるつもりだったが、終戦になり、師範学校(富山大学教育学部)に入学し、教員になる。
石動、砺波等の中学校、高校の英語教員を32年間行う。その後、金沢の専門学校、予備校に13年間、71歳まで勤務する。仕事を辞めてからは、富山の国際交流協会で病に倒れる平成28年5月(85歳)まで、月に1度、英字新聞の講師をしていた。義紀は30歳頃、小学校の教員である妻と結婚し、1女、1男を儲ける。
義紀は1945年(昭和20年)6月、15歳の時、志願兵として南砺市にある滑空訓練所で訓練を受ける。
「お国のためですので、理屈など抜きで志願しました。」
志願兵の応募者資格は、本来であれば操縦生徒は満17歳以上19歳未満、技術生徒は満15歳以上満18歳未満であった。いずれも高倍率のなか試験を通ったものが、日本各地の航空関連学校で一般教育を受け、その後修業1年の操縦者と、2年の技術者とに分かれ、いずれも卒業後は陸軍伍長に任官し飛行戦隊始め各飛行部隊に配属される。
しかし義紀の受けた滑空訓練はたった1か月であった。この1か月は「地獄の特訓」で、その後の義紀の生きる原点となる。
義紀は「世の中にどんな苦しいことがあっても、これ以上の苦しみはない。それからの人生はどんなことがあっても耐えられる」と思う。
8月15日、玉音放送を聞いたが、義紀は「神風が吹く日本。絶対負けるわけがない」としばらくの間、日本が負けたことを受け入れられなかった。
そのうち将来の不安が高まり、とにかく学校に行こうと思い、福野農学校と富山師範学校の入試があったので受験することにした。たまたま合格発表が早かった師範学校に入学することにした。師範学校は富山市にあり、自宅の小矢部から電車通学を行う。
通学の電車には大阪から進駐軍が乗ってきた。アメリカ人は高岡駅に停車中、ホームでタバコを吸ったり、チューインガムを噛んだりしながら英語をしゃべっていた。その様子を見て、なぜか英語を勉強したくなった。本屋で英語の本を求め独学するがなかなか英語力は高くならないことから、学校で英語を学ぶことを考える。このことが、英語の教師になるきっかけになった。
中学校、高校の英語教師、専門学校、予備校の英語教師と長い教員生活を送った。その間にはいろいろなことがあったが、何があろうと「あれ以上の苦しみはない」と乗り越えてきた。
晩年、入退院を何度か経験しているが、病気のことは淡々と受け入れ、自分らしく暮らす。何があろうと「あれ以上の苦しみはない」と考える。
2008年12月 左腎癌の摘出手術。8年後の2016年6月転移あり、病院にて後方除圧回避術施行した。病院に入院しているときの七夕の短冊に「茨道 峠の明かり見えてきた」と書いた。
病気になってからは特に感じたことは、「家族の支えのありがたさと、1か月間の滑空訓練の経験、この2つが自分を支え、『茨道 峠の明かり見えてきた』を信じて、残された人生も自分らしく生きていくことができると思った。
退院後12月に高齢者施設に入居する。どこにいても義紀は変わらない。なるべく自分でやってきた英語の力を衰えさせないように、英字新聞を隅から隅まで読む。気分が滅入った時でも、英語に触れていると気分が高まる。
施設の職員、家族、兄弟の自分に対しての期待が、今を生きるための励みになっていた。
2019年、88歳の義紀は帰らぬ人になるが、病院のベッドの枕元には最後の日も英字新聞が置かれていた。
あなたの物語 №7
~母親の一つ一つの言葉を運命のような感じがした。歳がいけばいくほど母親のことを思う。母親は神・仏と同じ存在~

みよ子は77歳の時、意欲低下、食欲減退著しく、老人性うつ病と診断され、精神病院に半年間入院した。退院後は金沢の長男夫婦が関わり自宅で生活したり、神奈川の娘の家で暮らしたりしていたが、2008年4月再び意欲低下、食欲低下で長男家族と同居し、精神科に通院しながら生活をした。主治医の勧めから、2010年(平成22年)5月に介護付き有料老人ホームに入居する。同施設は、脳活性化に取り組んでいたが、みよ子はそこで徐々に以前の自分を取り戻していった。認知行動療法を取り入れた14の教室活動、3つの懇談会、月3~4回行われる催し物、外出ツアーとほぼすべてのものに参加していた。その生活は2016年(平成28年)2月まで続いた。2015年10月うつ病が大分快復していると感じ、長男嫁と相談して7年間通院した精神病院から施設に近い診療所の精神科にかかりつけ医を変更する。新しい医師から「調子が良いので薬を減らしましょう」と言われ、本人は喜び、涙を流した。3か月後、徐々に気分が不安定となり元の病院に入院となる。元の主治医は「精神科の薬は飲んでいていい状態であれば服薬状態を変えないで、薬をメガネのようなものだと思って飲むものなんですがね」と説明があった。9か月間入院治療し、施設へ戻りゆっくりゆっくりの生活をスタートしたが、退院14日後脳梗塞を発症し、救急搬送された。入院中に再度大きな梗塞を発症し、施設を退去することになった。みよ子88歳の時である。
みよ子は1928年(昭和3年)3月31日に羽咋で生まれる。男2人、女3人の5人兄弟の上から4番目。尋常高等小学校、女学校(4年)卒業後、挺身隊で行った富山不二越工場で飛行機のベアリングの検査部で働く。その後、羽咋にも工場ができ移動する。終戦後は能登織物工場に結婚まで勤務する。20歳の時、高校の先生の紹介で三郎と結婚し、1女1男をもうける。子育て、家事をしながら、夫の自営の制服卸売業の仕事を手伝う。40歳の時、夫が逝去したため、呉服の販売の仕事を行って生計を立てる。呉服の販売は訪問販売をしたり、家の一室に呉服を置いて販売したりして70歳まで続ける。娘が夫の赴任先のオーストラリアでお産した時、数カ月間オーストラリアで孫の世話をする。76歳頃(2005年)までは詩吟など趣味を楽しみながら、羽咋で独居生活を続けていた。
みよ子は、4歳から母の手一つで育てられた。「6歳の時、学校で靴を取られた時『とったんじゃなくて、盗られたのでよかった』と母ちゃんが言った」など、母親の一つ一つの言葉を運命のように感じていた。歳がいけばいくほど母親のことを思う。母親はみよ子にとって神・仏と同じ存在であった。
晩年、みよ子が教室などで語ったあふれる言葉がある。そこには母への尊敬の念がたくさん語られている。また、自分の心を見つめた素直な表現がにじみ出ている。
「女学校の頃から続けている日記を書いている時が楽しく、大好きな時間。日記帳ではなく、ノートに書き新聞やイベンドで頂いたものなど記念になる物は貼っています。」
「ひ孫を授かったことが、何とも言えない喜び。今はただただ感謝の気持ちでいっぱいです。」
「新聞で梅がほころんだとか折々の話に触れ、寒い冬に堪えたたくさんの自然に感動します。・・・あんなに小さい渡り鳥が想像もできない距離を飛んでいく・・・・自然の神秘、不思議に感動し、励まされて生きています。」
「年を取るということは、周りの優しさを深く受け止められることができるようになるということです。」
「とにかく今日の日になって、自分が素直であることがなおさら大切だということを思いました。」
「(平成23年)10月20日、皇后陛下がだんだん自分の仕事の動作が遅くなってきましたと言われていました。また、物忘れのことに触れ、加齢のせいであるということも素直に受け止めたり、またそれでは困まることをバランスを取っていくことが必要と話しされていました。私も素直に受け入れて、寂しくなく、幸福であることを感じて生きたいと思います。皆さんのやさしさに心から感謝しています。」
「子供の頃、母親と一緒にあせもに効くとか言って塩水を汲みに海に歩いて行きました。丁度夕暮れで夕陽が見えます。その時の風景が嬉しいような、悲しいような景色として心に残っています。」
「好きな言葉は、普通の母ちゃんなんだけど、私は母を尊敬しています。その母が良く言っていた言葉ですが、『気は長く、勤めは堅く、色は薄く、食細くして心広かれ』です。」
「冬の日の思い出は・・・今年は大雪で今まであまり思い出さなかった冬の事を思い出しました。小さいころ道具の多い授業の日にマントを着て帽子をかぶって、雪に向いました。その時の姿を思い出して頭のてっぺんから、足の先まで母親の思いやりがいっぱい詰まっていて、母への思いがこみ上げてきます。」
あなたの物語 №6
~米作、ハルの物語(祖父母の物語)~

懐かしい祖父母(米作とハル)の物語を私の記憶と写真、そして「原戸籍」を辿りながら紡いでみます。
米作は1907年(明治40年)2月26日、黒部市村椿出島村に生まれます。島松次郎の5男2女の末っ子です。母が言っていたことですが、米作は地面に足が着くまで母親におんぶられていた甘えん坊だったそうです。
ハルは1902年(明治35年)2月20日、黒部市田家の山田源次郎の3女に生まれました。
この2人が結婚することになったのは、ハルが1929年(昭和4年)4月8日、27歳で松次郎の次男石次郎と三度目の結婚をしたことからです。石次郎は家の屋根から転落し、それが原因で翌年9月29日に逝去します。ハルは「石次郎とは3度目の結婚でしたが、前夫たちがぶおとこだったから出てきた。そんな自分に罰があたったから、最後まで誠心誠意看病をさせてもらった」。その様子をみた義父が5男の米作(24歳)と結婚させました。ハルは米作の5歳上の年上女房です。
2人の間には子供がいませんでした。1937年(昭和12年)9月8日に米作の兄磯次郎(長男)の次男忠一を養子に迎える。忠一は1927(昭和2)年3月27日生まれ。養子に入った年齢が10歳になっていたので、なかなか養父母の言うことを聞かなかったらしく、毎日のようにおもや(実家)に行っていたようです。忠一は隣村のとしと結婚しますが、としの亡くなった母親はハルの姉でした。ハルはとしの父親と相談し、忠一ととしが小さい頃に許嫁という約束を取り交わしました。
ハルが米作と5歳年下ということもあり、とにかく米作を大事にしました。
1966年(昭和41年)にハルは脳卒中で倒れ、1週間後の4月27日に逝去しました。享年64歳でした。私が8歳、小学校3年の時でしたが、ハルは草餅を作るために朝早くヨモギを摘みに出かけ、帰って来て玄関で倒れました。倒れてから1週間の間に親戚などの知り合いが近隣、遠方からもたくさんハルに会いに来てくれました。ハルは2度目を開けましたが、その時には「私が学校に行ったか」と確認したり、私の名前を呼んだりしました。玄関の一番近い部屋で、最後まで家族が側にいて看取りました。にぎやかで静かな1週間でした。祖母の葬儀、野辺送りにはたくさんの方が参列してくださいましたが、その光景をはっきり思い出すことができます。
私が1歳頃から、よく村の旅行などに連れて行ってくれたようで、写真がたくさん残されています。ハルは当時の女の人では背の高い方でした。私が近所の家の掘り炬燵の鉄瓶でやけどをして、母の実家でのお正月の集まりに行かないことにしましたが、夕方になって「お母さんの所に行きたい」と泣いたらしく、ハルは私を隣村まで負ぶって連れて行ってくれました。片道30~40分はかかると思いますが、何も怒らずに黙々と背負ってくれました。何かにつけ、私のやることに喜び、褒めてくれた祖母でした。

米作は1981年(昭和56年)9月12日、74歳で肝臓がんのため逝去しました。肝臓がんと診断され3カ月、最後の10日間は入院しましたが、亡くなる1年前の4月に、私の結婚式に参列し、7月に年寄り会で富士山のふもとまで旅行を楽しみました。亡くなる年のお盆のお墓参りの時、一緒に墓掃除に行った私に「最後やなあ」とつぶやいていた米作のちょっと寂しそうな後姿が目に浮かびます。
米作は30代前半、1937年(昭和12年)7月7日に勃発した支那事変で徴兵され、満州に従軍しています。
米作は「支那事変従軍記章」(勲章)を大切に仏壇にしまっていました。米作の寝床には軍服を着て馬にまたがる写真が柱にかけられていました。
米作が徴兵され金沢にいたとき、ハルは忠一の許嫁のとし(当時10代)を米作に合わせるために、金澤陸軍兵器支廠の兵器庫(現、金沢歴史博物館)で面会したという話を、としがよくしてくれました。

米作は、黒部の建設省に勤めていました。建設省は、1948年(昭和23年)1月1日から2001年(平成13年)1月5日まで存在していた日本の行政機関です。国土・都市計画、市街地整備、河川、道路、建築物、住宅政策、官庁営繕などに関する行政を取扱っていました。 現在は国土交通省に再編されています。米作は黒部川改修事務所(昭和33年~黒部工事事務所<建設省北陸地方建設局>)に勤務していました。60歳過ぎても働いてたと思います。
名前は米作でしたが、勤め人だったので米づくりは祖母と父母がしていました。米作は当時としては背の高いハイカラな人でバーバリーのコートなどを着たり、背広をよくオーダーメイドしていました。スクーターでなくオートバイにも乗っていました。近所ではどこの家より早くカメラがあり、白黒テレビ、カラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫など流行り物をいち早く購入していました。カメラがあったおかげで、たくさんの思い出の写真が残されました。
職場では現場の責任者をしており、優しい人だったので人夫(にんぷ)の人には人気がありました。現場によく私を連れて行きましたが、優しい親方の孫娘なので周りの人から可愛がられたことを覚えています。雪の日は夜中に電話で出動要請がありますが、現場に赴き除雪の指揮を執りました。冬の間は毎日のように電話がありましたが、祖父は嫌な声ひとつせず、家を出ていきます。
祖父は歌がうまいということで、慰安旅行などでも越中おわら節などの民謡、歌謡曲をよくリクエストされていました。その慰安旅行には私をよく連れて行ってくれ、歌の審査員をさせてもらいました。その時に職場の人にチューリップのじょうろをプレゼントされ、米作が大変喜んでいた顔が忘れられません。
米作の「越中おわら節」は素晴らしかったです。「一節一声」、一小節を息継ぎなしで歌います。一小節が終わるに従い音が高くなっていきます。
祖父の年齢の人で字の書けない人が村に何人もいて、よく書類の代筆をお願いされていたり、老人会の役員をして旅行などの世話をしていましたので、村のおじいちゃんおばあちゃんが毎日のように私の家に集って、お茶を飲んでいる風景を思い出します。

あなたの物語 №5
~「大いに東京の生活を楽しんでいます。本当にありがとうございました。」~

西岡さんは1924年(大正13年)1月1日東京で生まれる。2004年(平成16年)6月28日80歳で逝去するまで東京に住む。
1996年(平成8年)11月、西岡さんは妻と一緒に金沢のShining small stoneの「土地の人 旅の人」というお話会に参加した。その時の西岡さんの「気持ち」についての語りである。
「おじいちゃんが戦争時代、海軍で出会った友だちがいる。おじいちゃんは、その友だちは死んでしまったと思っていた。でも、その友だちは生きていて、一生懸命おじいちゃんを探してくれてた。今から 4年前、50年ぶりに電話がかかってきたんだ。50年も会っていなかったのに、その電話で声を聞いただけで、『やつだ』とすぐ分かった。それは2人の気持ちがつうじあっていたということ。それから年に一度会おうかということで、毎年広島に行くことになって、その帰りにここによることにしているわけだ。
今日のおはなし会の題は『きもち』ということだけど、人間というのはおじいちゃんの友だちがおじいちゃんに会いたいと思っていたように、思っているということがあれば、かならずつうじあえるということ。思っていないとつうじない。いくらやってもつうじない。だから勉強したいと思っていれば、勉強はするようになる。またできるようにもなる。したくないと思うと、したくもなけりゃしないし、ものごとが分からないような人間になるよね。勉強ばっかりじゃないよね。あの子と友だちになろうと思ったら、かならずその子と心がかようようになると思うしね。みんなで楽しく生きようと思う気持ちになれば、みんな楽しく生きられるようになる。世の中というものはまわりまわってくるもんだからね。みんなそういうような気持ちで楽しく生きてもらいたい。そういうことがおじいちゃんのいう気持ち。今日の『きもち』の集まりによろこんできたという気持ち。」
1997年2月、西岡さんからシャイニング・スモール・ストーンのお話会に集う皆に手紙が届く。
「シャイニング・スモール・ストーンの皆さん、お元気ですか。おじいちゃんが入院中といっても、去年の十一月から十二月にかけてのことで早くも二ヵ月になってしまいましたが、本当に激励のお便りをいただきありがたく、厚くお礼申し上げます。
シャイニング・スモール・ストーンの健さんがわざわざ病院まで見舞いくださり、 その際、皆さんの寄せ書きが贈られたのにはびっくりしたり、うれしかったりなんとも言いようのない感激に浸りました。
皆さんには、ただ一度お会いしただけなのに、それも何時間かの間のおはなし会だったのにもかかわらず、一人一人の方から絵入りのメッセージをいただくなんて考えてもいなかったのですから、その喜びは言葉に現わせないほどでした。しかも、初対面のお母様方からも励ましのコメントまで添えられて気恥ずかしさまで感じられるほどでした。
病院の看護婦さんも、わざわざ見せてくださいといって、うらやましげにのぞいていきました。西岡さんは塾の先生でもしているんですかと聞いていた人もいるほどです。病院の中ですから話題になった様子で、他の患者さんとも親しくしてもらいました。
ここの病院はミッション系なので、患者さんも修道士さんやシスターもいるし、看護婦さんはほとんどシスターで、礼拝や日曜教会もあり、おはなし会の本家みたい所なので、なおさら子供たちのメッセージが目についたのでしょう。
そんなことで、おじいちゃんは入院生活四十日を楽しく過ごすことができましたし、治療の方も順調に回復することができました。これは皆さんの励ましの声が大きく左右していたことを改めてご報告してお礼の言葉と致します。誠にありがとう存じました。 機会があれば、また皆さんにお会いして楽しい一日を過ごすことができますよう心から期待しております。今日は“地球”というテーマのおはなし会とのことですが、問題が大き過ぎて大変ですね。でも、人間は地球に足をつけてしっかり生きているわけですから日常のことは何でも“地球”にまつわることなのですね。そんな気持ちでお話を楽しんでください。東京は寒いといっても皆さんの金沢よりは暖かいようです。冬の金沢なんてロマンチックな気がしないでもありませんが、おなじ地球の日本の中で大した違いもありませんよね。
毎日を元気に自由に楽しく生活してください。おじいちゃんも、おばあちゃんも、大いに東京の生活を楽しんでいます。本当にありがとうございました。
スモール・ストーンちゃん達へ 敬具」
1993年(平成5年)7月、私たち家族が金沢に引っ越して来た翌年から西岡夫妻は毎年秋に金沢を訪れ、我が家に宿泊され、それに合わせて両親も一緒に時間を過ごした。懐かしい思い出である。
西岡さんと私が出会ったのは1984年(昭和59年)、印刷時報社という上野にあった出版社で働いた時からである。その会社では週間新聞の印刷ジャーナルと月刊誌などを出版していた「装丁コンクール」「カレンダー展」も開催していた。私が入職した頃には若手の記者が6人程いたが、西岡さんは私たちの指導員のような役割であった。その頃、西岡さんは60歳過ぎで、たばこをくわえ、赤ペンを持ち私たちの原稿をバッサリ切っていき何回もやり直しをさせられた。私の最初の原稿はほぼ全行赤線だったと記憶する。
最初は東京弁のべらんめえ口調の鬼の指導員という感じだったが、慣れてくるとその口調に愛情を感じるようになった。週間の新聞の締め切りが終わった日に、よく皆を飲みに連れて行ってくれた。よく行ったのは上野のガードレール下の飲み屋やビアホール、おしゃれな所で言うとプールバー。そして、常連客になった湯島天神下、不忍池近くの小料理屋風居酒屋三四郎にはちょくちょく行っていた。三四郎の上の方に新聞の印刷会社があり、週の半分はそこに詰めていた。三四郎のおかみとも仲良くなり、西岡さんは「編集長、編集長」と呼ばれ、焼酎に三四郎上げ、焼き鳥・・・どれもおいしかた。酔いが回ると西岡さんは『東京音頭』を歌い、皆で踊り出すのが常であった。仕事の話もしたが、クジラの養殖について真剣に語り合ったこともあった。周りにいた常連客とも顔見知りになり居心地のいい場所であった。
若い記者は過酷な仕事に音を上げ、辞めていくので出入りは何人もいたが、4人(周りからは四羽鴉と呼ばれていた)は比較的長く西岡さんと一緒に仕事をした。
西岡さんは四羽鴉を連れて水道橋だったか馴染みの「竹の子」という小料理屋風居酒屋や銀座のバーに連れて行ってくれた。突然の道行きになるので、持ち合わせがなく皆でできるだけ現金で支払うのだが、足りないお金は西岡さんが「つけといてくれ。おれの香典だ」と酔った勢いで言い出す。時には西岡さんの家にも押しかけたりした。西岡のおばちゃんは嫌な顔せず、迎えてくれた。私以外の3人は西岡さんの原稿を書く屋根裏部屋に寝かされていた。夢のような時間だった。
途中で分かったことであるが、四羽鴉の一人(九州出身だったと思う)の亡き父親と軍隊で一緒だったのが分かった、サムシンググレート。数年後、四羽鴉も退職し、西岡さんも仕事を辞めたが、西岡夫婦、娘さんとは家族ぐるみで、西岡さんが亡くなり、おばちゃんが亡くなるまで続いた。私の娘は西岡夫妻を自分の「おじいちゃん、おばあちゃん」と思って育った。その縁で、「土地の人 旅の人」のお話会への参加が実現できた。
西岡さんの「気持ち」についての語りと手紙を読むだけで西岡さんの「あなたの物語」を感じることができるが、私が覚えている西岡さんの物語を時間を遡り、調べながらもう少し綴ってみたい。
西岡さんは東京生まれの生粋の江戸っ子。1人息子。西岡さんは、明治学院専門学校(現、明治学院大学)在学中、1943年(昭和18年)に学徒出陣となり、霞ヶ浦海軍航空隊に入隊となる。そこで妻の兄と出会う。
学徒出陣とは、第二次世界大戦終盤の1943年(昭和18年)に兵力不足を補うため、高等教育機関に在籍する20歳(1944年10月以降は19歳)以上の文科系〈および農学部農業経済学科などの一部の理系学部の〉学生を在学途中で徴兵し出征させたことである。霞ヶ浦海軍航空隊とは、1922年(大正11年)大日本帝国海軍で3番目に設立され、1945年(昭和20年)の終戦まで存続した航空部隊。航空隊要員の操縦教育を担当した。(『ウィキペディア(Wikipedia)』参考)
戦後、職歴は分からないが、区報(広報誌)、業界紙などの記者・編集者の仕事をする。最後の職場印刷時報社だった。
「西岡さんはね、羽振りのいいときは頭にタオルを載っけて銭湯帰りにタクシーに乗って銀座に飲みに来ていたの」と銀座のママが言っていた。最後まで自由に生きながら縁を大切にするカッコイイ人だった。
あなたの物語 №4
~最後に思えたこと「生きてきたことこそが素晴らしいことなんだ。」~

かずひろは1947年7月7日、七夕の日に金沢に生まれる。3人兄弟の真ん中。地元の高校を卒業後、タイル職人として働く。
両親と同居し、父親が52歳で逝去した後、2007年に母親が85歳で逝去するまで2人で暮らす。弟は50歳代で肺がんのため逝去。母親逝去後、独居生活を送る。気ままに暮らし、近所に住む従妹が週3回食事を届けてくれていた。
2016年11月、仕事に出掛けようとしたとき、呼吸苦で病院を受診。入院となり検査を行う。大量の胸水があり、末期の肺癌胸腔内播種で、抗がん剤治療をしながら残された時間を施設で過ごすことを決心する。施設に入居したかずひろは、頭が空っぽになりどうしていいかわからなかった。職員には「少し前まで働いていたのに、もうダメなんだ。どう考えていいか分からない」言いながら、「今まで気ままに生きてきたのでマイペースに気ままにボーっとしていたい」と口にする。
兄は「かずひろは、時間があれば、ごろごろ横になっている生活、身体が病魔に侵されていても感じなかったという状況だったと思います」と言う。
かずひろが施設で過ごされた時間は7カ月だった。苦しい闘病生活だったが、職員に自分のことをぽつぽつと言葉にするようになっていた。施設の懇談会、忘年会、新年会、おひなさま、納涼祭などに参加した。かずひろのどの写真も兄が想像できない楽しいものだった。納涼祭でレイをかけ、アロハの声掛けに「アロハ」と自然に答える自分にびっくりもする。ジュースでの乾杯だったが、「乾杯!」と力強い弾んだ自分の声にも驚いた。
その年の「ゆく年くる年」という行事には体調が悪く参加することができなかったが、そこでパネル上演しながら朗読された『それでも僕は夢を見る』(文/水野敬也、画/鉄拳)のコピーを職員が届けてくれた。かずひろは、それを読んで涙が止まらなかった。「生きること、そのものが、輝きでした」 という一文が一番心に残った。なんにもなくても、夢破れても、なにも成し遂げていなくても生きてきたことこそが素晴らしいことなんだと思った。
翌年7月5日、息苦しいということで入院した。7月7日の誕生日にお見舞いのお花と、誕生日カードを職員3人が届けてくれた。かずひろは、経験したことのない出来事に素直にうれしいと思った。3人の職員がバースデーソングを歌い、七夕さまの歌を風鈴の音つきで歌ってくれた。「こんなこっとってあるんだろうか?」その日、かずひろは何度も思い返した。
入院してからは毎日、代わる代わる職員が会いに来てくれた。かずひろは苦しい呼吸の中、「こんなことって本当にあるのか?」と思いながら、自然ににっこりしている自分を愛おしく思った。
2017年7月14日、かずひろは享年69歳で逝去する。
「昨年12月に入院し、退院するにあたり、家に戻したらすぐに死ぬのではないかと思い、施設に入居させました。施設では本当によくしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
かずひろは結婚もせず、実直で仕事一筋という人生を送ってきました。華やいだ時間などなかった人生ですが、施設に入居し、若い人に声をかけてもらい、色のついた時間を過ごさせていただけました。本当にうれしいことで、私たちにとっても救いです。」
と、お通夜の時の兄が喪主の挨拶で述べた。
あなたの物語 №3
~それではと思い、好きな土地に行って働こうと思う…金沢から尼崎から東京~

れい子は、常々「死ぬことは怖くはないけど、後始末をしてないから簡単には死ねない。そして自分の死体の迷惑を掛けないようにしたい。」「生きたいとも死にたいとも思わない。人に迷惑掛をかけたくない」と言っていた。
平成20年9月S状結腸ガンの進行、肝臓・肺に転移。れい子は担当医のインフォームドコンセントのときガンの状態を自分でも確認し、「何もしないを選択したい」と言った。その後もぎりぎりまで飄々と高齢者施設で生活した。周りから心配されても、「病気のことなど覚えていない」と何もなかったように答える。そして「物覚えが悪いのは、私はもともと自分に関係ないことは覚えないようにしているからね・・・・」と笑う。平成21年7月、れい子は85歳で帰らぬ人となった。本人が心配していた亡骸は輪島で荼毘に付され、実家のお墓に納骨された。
れい子は大正15年1月、輪島の蒔絵師の家に8人兄弟の上から5番目に生まれる。尋常高等小学校卒業後、縫製工場に1年間働くも、何か身につけたいと思っている時に、朝日新聞の広告に京都大学の看護婦学校の募集を見て上京する。3年間の看護学校を卒業し、従姉妹の薦めで、金沢で勤務を考える。3人の医者からプロポーズされたが、本人には足のコンプレックスから、結婚については考えたことがなかった。20歳から20年間2か所の国立病院に勤務する。20年間勤務すれば厚生年金がもらえると思い退職するも、制度的な勘違いで一時金しか下りなかった。それではと思い、好きな土地に行って働こうと思う。まず兵庫県尼崎市の診療所で1年間勤務し、その後、東京に移住して日本通運健康保険組合東京病院の病院に1年勤務し、東大病院に昭和60年、60歳まで勤務する。
退職後は自然観賞を楽しんだり、音楽を鑑賞したり、相撲を友達と見に行ったりとゆったりした暮らしがつづく。住居は昭和49年千葉のマンション住まい、昭和53年から自分の好きなものに囲まれた趣味のいい一軒家でペットの猿といっしょに暮らし充実した日々を過ごす。洋服は気に入ったものを長く着るタイプでそんなに買わないが、雑貨は好きで、家に来た人達は“素敵な部屋”と言ってくれた。部屋毎に雰囲気のあった家具やカーテン小物を置いていた。
そのうち猿が亡くなり、千葉での独居生活に防犯の面で不安を持つようになり、兄弟からの勧めもあり、平成17年4月から金沢に移住することに「何となく」なる。
れい子の上には兄が4人にいた。長男は戦地から一旦戻り、家業を継ぎたかったが父とうまくいかなかったようで、神戸で輪島塗の商売を始めた。次男は戦死した。次男は無口で、優しい誰からも好かれるタイプで、外見もよかった。三男は戦地から帰って県外に行った。四男は戦地から海を渡って逃げてきた。
長男は世界の文学全集などを読むのが好きで、蔵の2階にその全集や雑誌が置いてあり、れい子は小さいときから文学全集を読んでいた。本の影響もあってか、「人を恐れるとか、遠慮するとかはしないタイプ」になった。蔵で初めての本に会った時のドキドキ感は忘れられない。
その当時、京都の看護婦学校に行くことができたのは、戦争中に「女でも家に置いておくと戦地に連れて行かれると」噂が立っていたので、両親は何も言わないで出してくれた。
「京都の病院に18人入院患者がいる部屋があって、偉そうにしている看護婦達でも、泣きべそをかいて出てくるような患者がいた。私がその部屋に入ると『ムッソリーニと片手を斜めに上げて』敬礼してくれた。その部屋の一人に何のことか聞くと『ムッソリーニは英雄だから』と言われた。」
また、あの頃のことではっきり覚えていることがある。医者に頼まれて入院していた人を都ホテルに送っていった。都ホテルに大変興味があった。その女の人をホテルにいた男の人の所に送っていったが、その後、『新潮』という雑誌にその女の人の写真が載っていたが、その人は女優の桂珠子という人だった。
れい子は人生の中でずーっと申し訳ないと思っていることがある。 自分が偉業をしたいなどと思ったことはないから、振り返って後悔するようなことはなにもない。目の前に頼ってくれる患者さんを看護することだけ考えて仕事をしていたから、どこの病院の仕事がどうだったとか思ったことはない。ただ、尼崎で1年間働いた診療所の院長には申し訳ない気持ちを持っている。大阪駅から神戸側へ2つ目の駅だったと思うが、新聞記者がここはこわいところなのに大丈夫かと聞かれたことがある。こわい人が集まっているところだったが、そこの院長はどんな患者でも、何日もお風呂に入っていない人でも頼ってくる患者の面倒をみる医者だった。どんなに暴れる人でもその医者が一言怒鳴ると子供のようになった。そんなすごい院長に辞めないでくれと言われたのに、東京に行ってしまったことが、申しわけないことだったと今も思う。病院の名前は「とのうち(戸ノ内診療所)」だった。(※戸ノ内診療所は2023年3月31日をもちまして閉院。69年間の幕を閉じた)
れい子は施設の喫茶などで周りの方と楽しく話をするのが好きだった。れい子と周りの人とのユーモアに富んだ話が飛び交う。眉毛が長い男性に「その眉毛は自毛ですか?」と聞く。「自分の毛や」と相手が答えると、「そんなところカツラでもないし、立派な眉毛ですね」と言う、相手は「わしだけやこんな眉毛してるのは」と言う。その後、髪の毛の話になり、相手の方が「髪の毛がごわごわして広がる。今は少しましになった。昔は広がるので、パーマをあてていた」と話す。れい子は考え込みいきなり笑いだし、「あなたのパーマは想像できないわ」とまた考え込む。もう一方には髪のない方だったが、その方に「髪の毛の無いのは、いろいろと下(子・孫・ひ孫)に譲っているからだ」という。周りは大きな笑いが湧きおこる。
そんなれい子の晩年だった。
あなたの物語 №2
~教員生活62年、「休まず、遅れず、働かずの弥一です」と弥一は胸を張る~

「今から考えると、誇大妄想的でおかしいことですが、 若い頃は何でも自分の力でなれそうな気がしていたのです。 まず、弁護士になれば、やがては代議士ぐらいになれる、そして、すえは総理大臣になれるかもしれないと思ったのです」 16歳で教壇に立ち、総理大臣を目指した弥一は、明治37年(1904年) 3月30日、 岩手県和賀郡笹間村 (現花巻市)の小作農の長男として生まれた。大正時代の風雲に乗じ、独学で教壇に立ち、純真な野心を持って東京にやってきたの である。
「夢は大きい方がいいですからね」と、 照れながら話すが、当時の弥一青年にとっては、総理大臣は夢物語ではなく"大志は必ず実現できる”という意気込みだったのである。
「いつか、生徒の前で、わしは総理大臣になろうと思っているんだと言ったら、総理大臣じゃなくて、草履大臣だ!とひやかされたものです」と、過し日の思い出を振り返える。
当時、学資に乏しい子弟の進む道は、学資官費の師範学校か幼年学校、でなければ夜間の鉄道学校しかなかった。尋常高等小学校を卒業した弥一は、師範学校の試験を受けるのだが、身体検査でトラホームが原因で落とされてしまった。しかたなく、農業に1年間従事、ついで村役場の雇(現書記補)として1年間勤務するが、その間も独学で勉強に励んだ。弥一の青年期は、大正デモクラシーの高まりで、自由と個性を追求する雰囲気が民衆の中に浸透していった時代であった。
大正9年、将来につながる幸運が訪れた。恩師が代用教員の口を見付けてくれ、16歳で教壇に立つことになったのである。代用教員になった年の12月に教員検定試験を受け、尋常小学校本科教員の免許を、ついで、翌年12月小学校本科正教員免許を取得した。これは順調に師範学校を卒業する年数(5年)よりも1年3カ月早かったというが、今の高校生諸君には、信じられないことであろう。
岩手県は、山地が多く、しばしば冷害や水害が起こり、食糧などの生産性が非常に低い時代が長くつづいた。人々は、きびしい自然に耐え、窮乏と戦いつづけ、その鬱積が、地方劣等感と中央憧憬を根強くさせたという。原敬、斎藤実などの政治家もこの県の出身者である。弥一の心の中にも、"東京"への瞳れがふくれあがっていた。小さい時から、たまにしか手に入らない新聞の東京の求人案内をすみずみまで見て、上京する機会をうかがっていた。教員になれたことを幸いに、大正12年春、東京市教員採用試験を受け、合格となった。2ヵ月間の研修を受ける東京市教員講習所の入学式の日に上京しようとするが、その日は折りも折り、あの関東大震災の起こった9月1日であった。そのため、ふたたび岩手の小学校で教鞭をとることになった。大正デモクラシーが高まる一方、大正7・8年頃から、米騒動、シベリヤ出兵、戦後の恐慌、第1回メーデーといった世情不安で騒然としていた。それに加え、関東大震災が起こり、民衆の生活は、まさに野口雨情の『船頭小唄』に象徴され、気持は沈みがちであった。
しかし、弥一の情熱は消えず、一日千秋の思いで東京への再出発を待ちつづけ、ついに半年後の大正13年に上京することになった。20歳で当時の日比谷小学校で教壇に立ちながら、遙かな目標への一歩、すなわち弁護士を目指して勉学に励むのであるが、思うようにいかず、法学通論を手掛けた時に壁にぶつかってしまった。「計画を立てて、図書館に通いながら勉強しましたが、あまりに難しくて、途中であきらめてしまいました」 と、 独学での自分の限界を悟る。
そこで、どうせ教師の道に一生を賭けるのなら、数学をやりたいと思い東京物理学校(現東京理科大)を目指し、願い叶って入学となったが、保証人の手続きが遅れたため、入学を取り消されてしまった。
はた目には、ほぼ直線のごとく見える川筋も、本人にとっては迷いの連続であった。弥一は、挫折感をかみしめながら、これを機にむやみにあがくことはやめ、地道に自分のもらった土壌に根を 降ろし、大木になろうと思った。
昭和39年から中学校校長として退職するまでの44年間を小中学校の教育にたずさわり、その後、女子大学学生課長12年、嘱託として6年間学生指導にあたった。78歳まで教職を天職として、ひたむきに 勤めあげた。
62年間の教員生活の中で、1日も休まずに勤めあげたことをたったひとつの自慢だと言って胸を張って、「休まず、遅れず、働かずの弥一です」と笑わせる。 しかし、教員を志している者の中で何人が、弥一のたったひとつの自慢を実現できるであろうか。
弥一のもの腰は、実に温かくて、博識と回転の早いユーモアに半世紀以上の年齢差も忘れてしまう。こういう態度は、誰に対してもそうであって、相手の社会的地位や、職業、年齢など全く無関 係である。 「生まれつきか、学校生活を経験しなかったせいもあるのか、人間関係についてもこわいもの知らずになっているのです。それが欠点でもあって、恥をかいたこともいっぱいありますし、にらまれたこともあります」 と言うが、損得を考えないで、自然に自分の意見を言える弥一には、硬骨とした精神と少年のような純粋さを感じる。
「教育というのは、一人ひとりを大事にすることであると思ってきました。どんなにできない子供でも、一人ひとりの個性を大事にはぐくもう!というのが私の教育の原点でした。なぜなら落ちこぼ れみたいな生徒とか、寝ているか起きているか分からないのでお客さん呼ばわりされている生徒でも、心の中では、いろいろなことを考えているものです。そういう人間性を大事にしてやらなければ、なんのための教師でしょうか」というのが、弥一の教育理念であるが、そういう落ちこぼれに対して、非常に冷淡になってきていると心配する。 "人生” のことは分からないと言うが、 教育観がそのまま弥一の人生観とも言える。「世の中は、この30年なり50年の間 に偏差値評価というのが骨の髄まで染み込んで、人間の見方を点数だけで評価するようになってきました。 今の臨教審は、その悪い流れに乗っていると思うのです。 こういう状態で、修業年月がどうとか、カリキュラムがどうとかという問題に取り組んで制度を変えようとしても上っ面だけを走っているようなもので、本当の教育は出来ません。 “天は人の上に人を作らず”ということばがありますが、 最近では“点は人の上に人を作り、人の下に人を作る”という弊害が横行しています。 そして、世の中が、 その弊害を弊害と思わないところにこそおそろしさがある・・・と、古い教師は危機を感じています」と教育人生を生き続ける。(昭和61年2月の弥一の言葉。弥一は99歳で亡くなる。)
「勉強がらくになるためには、受験生であっても、本当に自分のやっていることに興味を持つということが必要だと思います。もちろん目的を決めてやることも大事ですが、自分が勉学をしているのに、勉強に興味がないと、ただ暗記しなければならない、合格しなければならないということだけが先行してしまいます。それでも、いい大学に入れるかもしれませんが、将来にわたっての本当の勉強の土台というものができてこないのです。
今の人達は、よくマンガを読んでいるといわれていますが、マンガも本当に興味を持って、その奥に入りこめば、その中に人生観を見い出すことも出来ると思うのです。興味をもてば、知識が確実になり生涯の力になります。皆がいくから大学を受けるのではなく自分にとって興味のものがあるからこそ、大学を受けるのだ! という自覚を持ってください」 とこういく人過ぎに生きる弥一は語り続ける。(昭和61年2月の弥一の言葉)
あなたの物語 №1
~いつも不足を言わず、家族に満足し「まあ、最高に幸せやね」が口癖だった~

忠一は昭和2年3月27日、富山県黒部市に生まれる。3男3女の上から3番目。幼少の頃、叔父夫婦の養子となる。尋常高等小学校卒業。15歳の時、飛行機に憧れて東京立川の日立航空(株)の青年学校で学びながら飛行機工場で働く。忠一は、子どもの頃はやんちゃなであったため、校長先生も心配していたようだ。日立航空の青年学校に合格したのが学校で2人だけだったことから、全校生徒の前で校長先生は涙を流して喜ばれていたと言う。
忠一は18歳の時、兵隊検査を受け、甲種合格となるが、航空で働いていたため、戦地に行かなかった。東京大空襲の時、工場は爆撃される。工場にいたほとんどの人が亡くなった。忠一は、まさにその時、腹痛に襲われトイレに行っていた。一瞬の出来事だった。黒部から一緒に来ていた友達も戦火の中で亡くなってしまう。終戦直後の昭和20年8月20日に黒部に帰郷し、友の家に骨壺を届けた。その時の友の両親の涙は一生忘れられなかった。
その後、養父が建設省に勤務していたため、家の農業を主に行い、冬場は東京などに出稼ぎに行っていた。
小学校の同級生や村の幼馴染、兄弟との絆は強く、晩年まで行き来をしていた。忠一は身長155センチほどしかなかったが、農業や肉体労働で鍛えたがっちりした体格で力持ちだったため「熊の忠さん」と呼ばれていた。また、性格的にはやんちゃで、きかんぼうだったが、人情に厚く家族、親類、友達や近所の人を分け隔てなく大切にする人物で、縁の下の力持ちとして「石の盤持つ」「花棒」と周りから言われていた。
天真爛漫な性格は晩年まで続いたが、破天荒な面もあり、家族特に妻は大変苦労した。こんな出来事があった忠一60歳の頃、小学校の同級生の一人で指定暴力団の幹部がおり、同級会で還暦の祝いをするときに黒部に来ることになった。その同級生は親も亡くなって、宿泊先がなかったので、忠一は妻のとしには素性を言わず、家に泊めることにした。としは忠一の友達をもてなすために一生懸命手料理を作った。いざ、その友達を見たとき、異様な感じがしたという。腕に金鎖、黒い背広、サングラス、・・・・身の毛がよだった。どうしていいか分からず、早く立ち去るのを静かに待った。翌日、子分2人が車で迎えに来た。
その日、としと大喧嘩になるが、忠一は「かわいそうな。泊まるとこもないし、親戚も知らん顔やからね。糖尿病にもかかっとるし」、「子分も大人しく、挨拶もきちんとしとった」と言う。襲名披露?にも呼ばれたりした。勿論、家族が行かせなかった。その後もその人が亡くなるまで時々電話が来ていたが、家族には「かわいそうやねけ」が口癖だった。
昭和30年~40年代頃は時々家に「乞食(物乞い)」が来る時代で、忠一はそのたびに10円玉とバナナを渡し、いやな顔をしなかった。また、宗教活動の子供づれのグループが家に時々やってきたが、その時も台所から必ずバナナを持ってきて子供たちに一本一本渡していた。その根底には「かわいそうやねけ」がある。
バナナは忠一にとって特別な果物であった。忠一に限らず昭和30年代までは、バナナは高級なもので特別なものだった。忠一は自分の子供たちにも、お金が入った時には必ず大きな房のバナナを買ってきた。
忠一は出会った人とすぐに仲良くなり、人脈づくりにたけていたのは、破天荒だが憎めない人柄からくるのだろう。
忠一は昭和27年(25歳)の時、養母の姉の子供であるとしと結婚した。としの母親はとしが小学校の頃田んぼで倒れなくなった。養母ととしの父親が行き来のあったことから、忠一は子供の頃から、としの実家に農家の手伝いをしたりと、よく出入りをしていた。としの父親は働き者の忠一を大変気に入っていた。としには心に決めていた人がいたが、許嫁同然だった忠一と結婚することになる。忠一はとしとは5歳違いであったが、としのことを子供のころから好いていた。
としが家で洋裁をしているときなど、窓からチョコレートを投げてプレゼントしたり、盆踊りの時には、村一番の美男子に頼んでとしを自転車に乗せさせたりと自分なりにとしの機嫌を取っていた。
最愛の人と結婚できた忠一だったが、「やんちゃもん」だったため、言葉遣いは荒く、なかなかとしが望んでいるような日常生活は実現しなかった。また、忠一は田んぼ仕事は「ねんしゃもん(丁寧にやる)」だが手が遅く、としの仕事がだんだん増えてくる。
昭和33年に長女、昭和36年に次女をもうける。徐々にとしも強くなり、2人の間は喧嘩が絶えなかった。
長女が生まれたことをきっかけに米以外にたばこ栽培も12年間行う。長女を当てに農業をやっていたが、徐々に限界を感じ昭和45年(42歳)でたばこ栽培を辞め、建設会社(生コンを作る機械操作)に55歳の定年まで勤務する。
昭和42年、40歳の時、姑を家で看取り、舅も最後の最後まで寄り添って昭和56年に見送った。昭和56年長女の結婚、昭和62年孫娘が生まれる。
退職後、1年間技能学校に行き、その後、58歳の時、建設会社に勤務するが、機械整備中に7メートル落下し、両足と顎を複雑骨折し、3ヶ月間入院し、リハビリ通院を続ける。昭和63年、次女の結婚後夫婦2人暮らしとなる。
忠一は、60歳から73歳まで、米やネギ栽培をしながら鉄筋会社、建設会社で働く。米作りは81歳まで行う。畑仕事は平成25年秋(86歳)まで行う。
車の運転は86歳の時返上する。その後、電動自転車に乗り、買い物や銀行、農協などの用足しを行なっていた。平成26年(86歳)2月6日、金沢市の長女家族の近くにある高齢者住宅に夫婦で入居し、1年5か月をとしと隣同士の部屋でデイサービスを利用しながら暮らす。金沢に来るまでは、身体も達者だったので、北海道、沖縄、城崎、奈良、長野など毎年家族旅行を楽しんでいた。旅行の思い出は家族の宝物となる。
平成27年7月6日、レビー小体型認知症のパーキンソン症状の悪化により医王病院に入院する。医王病院では孫娘が主治医となる。その後、地域密着型特養に入居する。家族はコロナ禍の中でリモート面会を続けていた。熱発を機に忠一の身体状況が悪化のため、短時間の面会が許され、家族と1年ぶりに直に会うことができた。令和3年3月3日はサムシンググレートなことが起きた。ひ孫と初めての対面。忠一は細く目を開けひ孫を見た。娘が「お父さんのひ孫だよ」と言うと、目を開いて分かったという満足した表情をした。令和3年3月12日、同じ階に入所していた最愛の母の側で満足した人生を閉じた。
忠一はいつも不足を言わず、家族に満足し「まあ、最高に幸せやね」とよく言っていた。短気で妻を怒りつけたりしていたが、妻がいなくては何もできない人だった。子供を大切にし、孫娘を大変かわいがった。背の小さい忠一だったが、力持ちで家族にとっては頼れる父親だった。
忠一は晩年傾眠状態が長くなり、語彙も少なくなり会話もままならない状態になっていたが、時々忠一らしい面白い顔や言葉を言ってくれた。忠一の得意な言葉は「そうそう」「ほんじゃから」。元気な時は「しっとるちゃ」「しらんちゃ」の2ワードを中心に会話をしていた。

